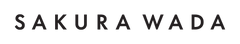東洋医学の「気」を解説!働きからケアする方法まで
東洋医学では、人間の体を構成し生命活動を維持するための要素として「気」「血」「水」の3つを重要視しています。東洋医学で健康を語る上で欠かせない存在です。
今回は、そのうちの「気」がテーマ。体の「気」を充実させて、エネルギーに満ちた生活を送るための方法をご紹介します。
そもそも「気」ってどんなもの?
曖昧なイメージはあってもなかなか捉えづらい「気」。具体的にどういった働きがあるものなのかご説明します。

「気」は体を動かすためのエネルギー源
東洋医学において「気」とは、体を動かすための根本的なエネルギーのことをいいます。
人間の体は、自分の意識とは関係なく呼吸や消化吸収、血液循環を行なっていますよね。このような生命活動を推し動かしてくれているのが「気」なのです。「気」がないとそもそも人の体は動きません。
また、「やる気」や「元気」などの言葉に使われるように、気力や体力など活動するためのエネルギーを指したりもします。
「先天の気」と「後天の気」の2種類がある
「気」は、ひとが生まれながらにもっているものと、生まれた後に培っていくものの、大きく2種類に分けられます。
先天の気(せんてんのき)

両親から与えられ、生まれながらに持っている「気」を「先天の気」といいます。
先天の気は生まれたときが最も多く、年齢を重ねるにつれて減少します。さらに、加齢だけでなく乱れた生活習慣やストレス、病気も減少の要因に。
後天の気(こうてんのき)

先天の気が生まれ持った「気」であるのに対して、後天の気は生まれた後に獲得する「気」です。
食べ物や飲み物を摂取することで作られる「水穀(すいこく)の気」と、呼吸によって取り込まれる空気から作られる「清気」の2つがあり、2つの「気」が交わることで後天の気が生まれます。
加齢により先天の気がなくなるのを補うためにも、自分の体質に合った適切な食事を摂り、後天の気を充分に取り入れることが重要です。
「気」にはどんな働きがあるの?
からだを動かすエネルギー源である「気」。具体的には体や心にどのような働きをもしているのか、ご紹介します。

東洋医学において、「気」の主な働きには以下の5つがあります。
気の働き①推動作用(すいどうさよう)
さきほども触れたように、成長発育、生理活動、血液循環、神経活動、代謝などの基本の生命活動を推し進めているのが「気」の推動作用です。また、体を構成する3要素の「気」「血」「水」ですが、「血」と「水」を体中にめぐらせる働きを持っているのも「気」です。
気の働き②防御作用(ぼうぎょさよう)
体を守る免疫機能・抵抗力のこと。ウイルスから体を守り、病気の原因となる「病邪」と戦います。そのため、「気」が不足していると免疫力が下がり風邪を引きやすくなります。
気の働き③温煦作用(おんくさよう)
体を温める働きのこと。「気」により、体温が一定になるように調整されます。
気の働き④固摂作用(こせつさよう)
体にとって必要なものを体の外に出ないようにする働き。発汗や排尿などに関係していて多汗、頻尿などの異常が起きないようにコントロールします。
気の働き⑤気化作用(きかさよう)
体内の物質を変化させる働きのこと。物を食べると消化、吸収されたあと体に必要な「気」や「血」「水」に変化します。この変化が気化作用です。不必要な水分を尿や汗として排出して代謝を促す働きもあります。
「気」にまつわる不調タイプとケア方法
体の活動エネルギーである「気」にトラブルがあると体にさまざまな不調が起こります。「気」の不調が出る代表的な2つのタイプと、それぞれの改善方法についてご紹介します。
①「気虚(ききょ)タイプ」気が不足した疲れやすい状態
「気」が不足している時に現れる不調。原因は必要な栄養を摂取できていない、胃腸が弱っていて栄養を吸収できていない、過労によるエネルギー不足などがあります。
気虚の不調

気が不足している状態で、何かと疲れが出やすく、やる気も出ない場面が多いです。以下のような不調が出る傾向があります。
- 疲れやすい
- やる気がでない
- 汗をかきやすい
- 動くと息切れする
- むくみやすい
- 冷えやすい
- 風邪を引きやすい
- 頻尿
- 軟便、下痢になりやすい
気虚をケアするには
「気」を作り出すためには、偏った食事をせずに「気」を補う補気食材を摂り入れながら栄養バランスのよい食事を心がけることが大事。また、胃腸が弱っている状態なので、冷たいものや脂っこいものは控え、消化のよいものを選びましょう。
「気」を満たすには睡眠も大切。早めにベッドに入り、しっかりと睡眠をとるようにしましょう。また、過労や激しい運動を避け、無理をしないことも大切です。
おすすめの補気食材や詳しいアドバイスはこちらもご覧ください。
おすすめのブレンド

紅茶、なつめ、乾燥生姜、朝鮮人参をブレンドした健康茶。じんわりと温まり、ほのかに甘く元気が出るような味のお茶です。
②「気滞(きたい)タイプ」自律神経が乱れて心身に不調が出る状態
「気滞」という文字の通り、「気」が正常に循環せずに滞っているのが「気滞」タイプ。いわゆる自律神経が乱れている状態です。
気滞の主な原因はストレス。単なるイライラだけでなく、忙しさ、プレッシャー、抱え込みなどもストレスに入ります。責任感が強い人は気滞になりやすいと言われているため、要注意。
気滞の不調

気が滞ることで、体だけでなく精神面への影響も出やすくなります。以下のような不調が出る傾向があります。
- ため息をつく
- イライラしやすい、情緒不安定
- 落ち込みやすい
- 胸がつかえる、圧迫感がある
- げっぷやおならが出る
- 便秘になったり軟便になったり不安定
- 寝つきが悪い
- 生理周期が不安定
- 生理前に胸が張る、PMSが出る
気滞をケアするには
リラックスをして、ストレスを溜めないことが大切です。ストレスを溜めないというのは難しいことではありますが、深呼吸をするだけでも違いますよ。好きな趣味を楽しんだり、軽い運動をしたり、お風呂に浸かったり、リフレッシュできる自分タイムを設けましょう。
騒音や強い光などの外的要因によってもストレスを受けてしまうため、心地よく過ごせる環境に身を置くのも効果的。ハーブやアロマなど好きな香りでリラックスすると、体の中の「気」が正常にめぐっていくのでおすすめです。
また、気滞は食べ物からもケアできます。気をめぐらせる理気作用のある食べ物を摂り入れてみてください。
おすすめの理気食材や詳しいアドバイスはこちらをご覧ください。
おすすめのブレンド

ジャスミン茶、キンモクセイ、蜜柑皮、ウコンをブレンドした健康茶。香りが華やかで、気分よくお飲みいただけるお茶です。
まずは自分のタイプを知って適切な「気」のケアを
不調の原因は一人ひとりの体質や状態によりさまざまです。気になる不調を改善するために、まずは自分のタイプを知ることからはじめましょう。
日々の生活のエネルギー源「気」を充実させましょう
東洋医学において「気」は体を動かすためのエネルギーであり、「気」に不足や停滞などのトラブルがあると不調が生じます。
①気虚タイプ
「気」の不足が原因。ケアするには栄養バランスがとれた食事や質の高い睡眠が必要。②気滞タイプ
「気」の停滞が原因。ケアするには、リラックスを心がけてストレスを溜めないことが大事。

体や心を日々見つめて「気」の変化を感じ取り、「気」を上手にコントロールしてエネルギーに溢れた日々を過ごしましょう